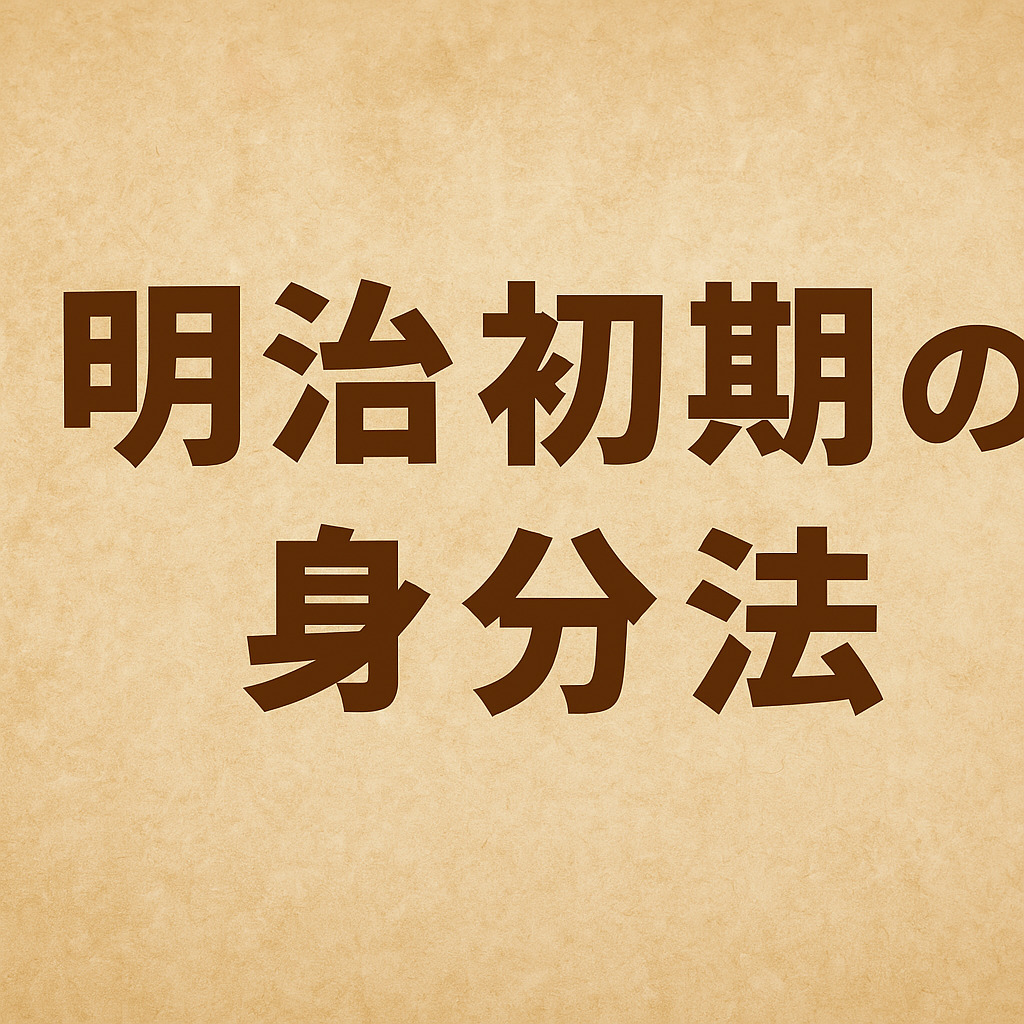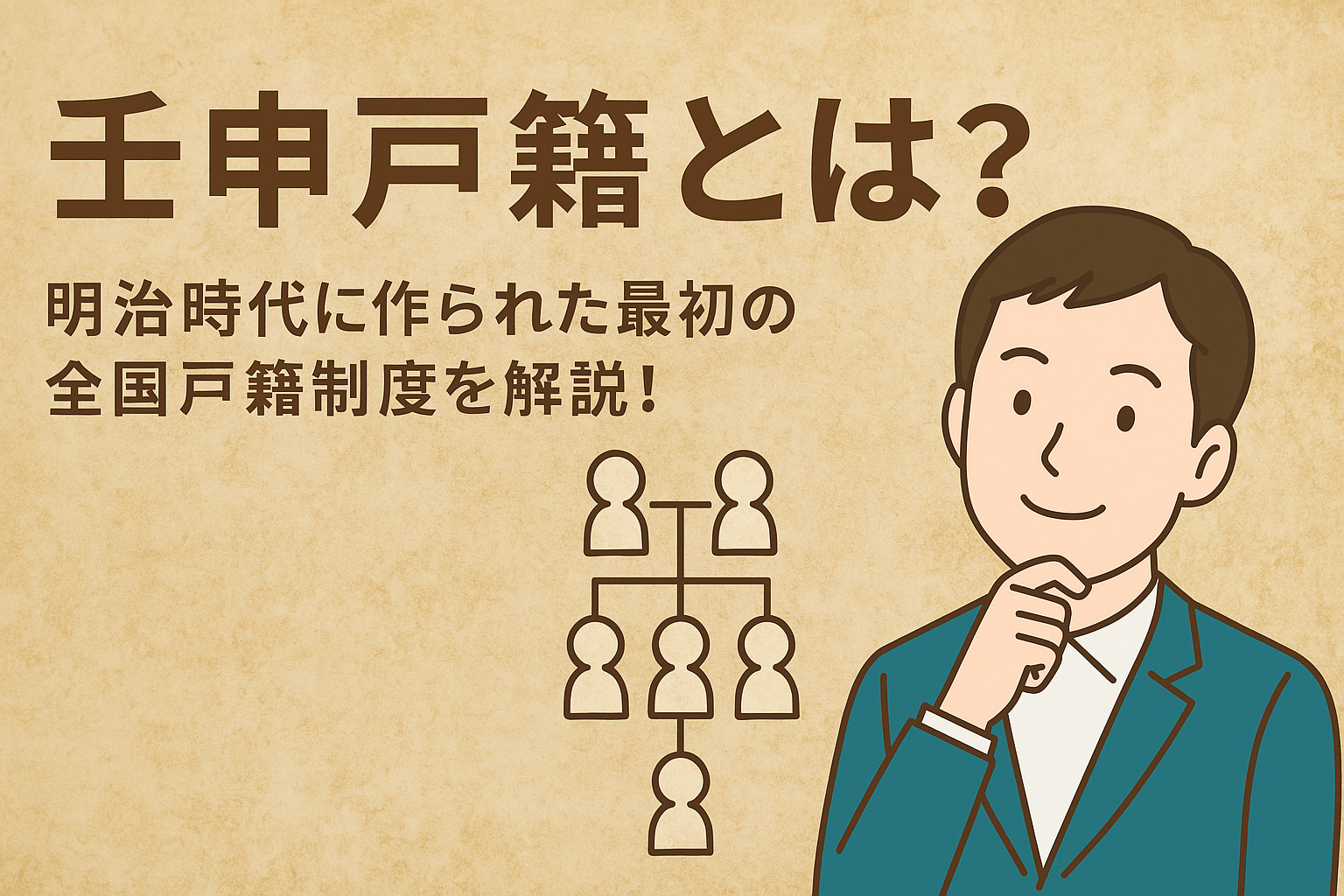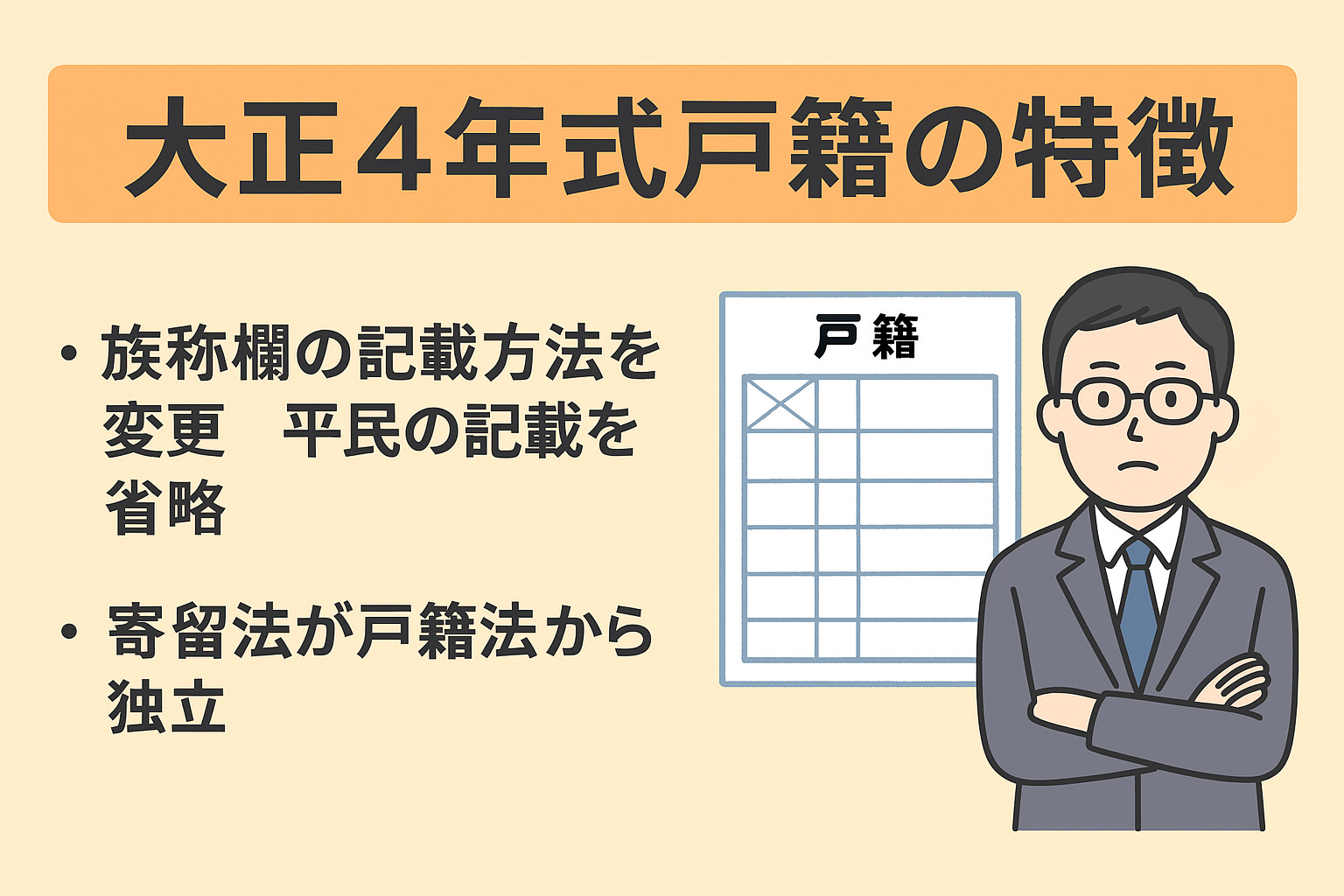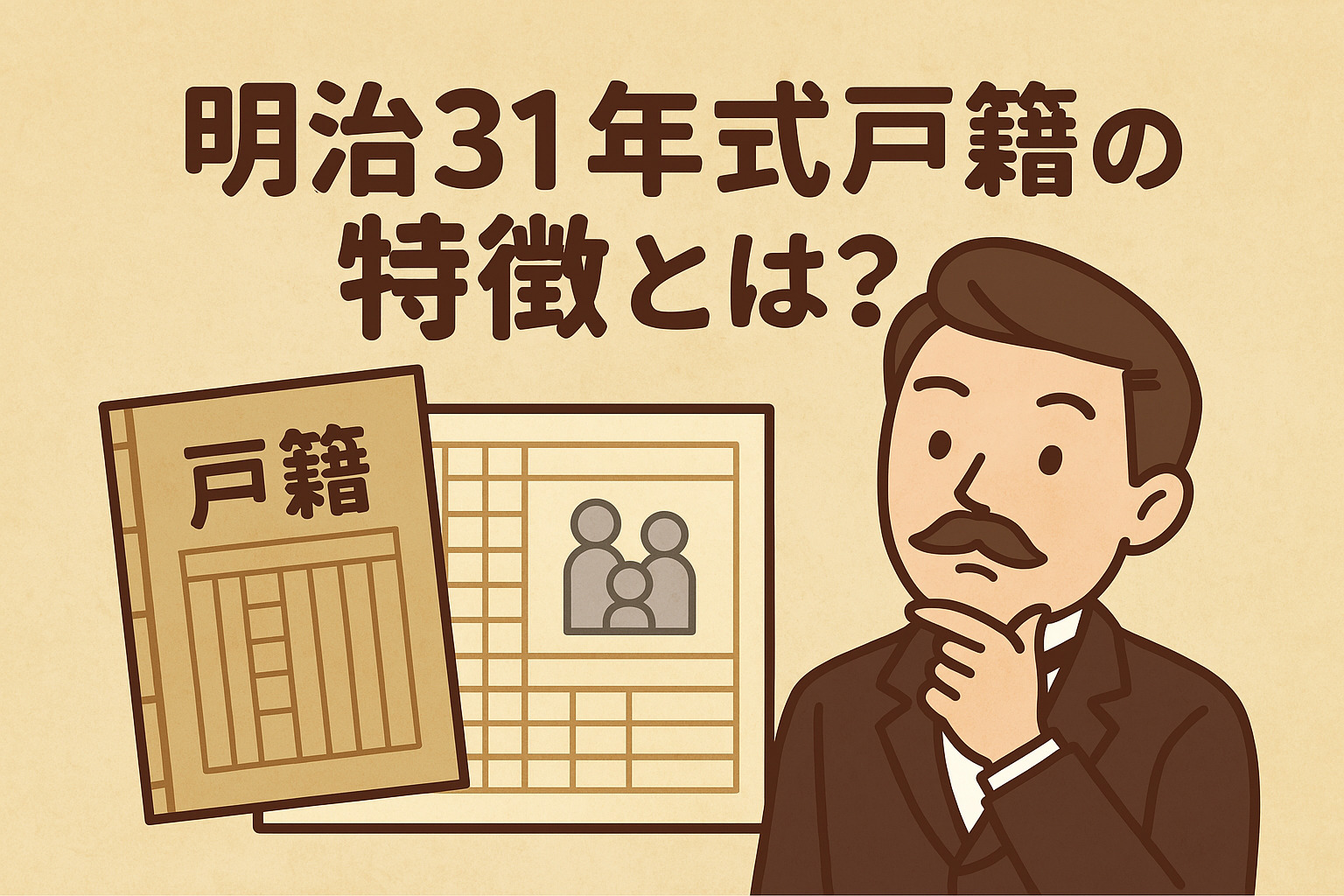「先祖が戦時中、外地で暮らしていた」「終戦を樺太や満州、台湾で迎えたと聞いている」
そんな方にとって、家系図作成の出発点となる資料の入手は、特に難しく感じるかもしれません。
ここでは、樺太・外地終戦者の家系調査方法について、現在利用できる資料やその取得方法をわかりやすくご紹介します。
【よくあるご質問②】除籍の取得・家系図作成に関する疑問にお答えします!
家系図を作成する際には、「どこまで取得できるのか?」「どこで何を調べればいいのか?」など、さまざまな疑問が出てきます。
今回は、実際によくいただく質問と、その回答をわかりやすくまとめました。
【よくあるご質問】家系図作成・ルーツ調査について
家系図作成に関心はあるけれど、「どこまでさかのぼれるの?」「どうやって調べればいいの?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
ここでは、家系調査の現場でよくいただくご質問と、その回答をわかりやすくまとめました。
【家系図作成に役立つ!】オンライン検索&デジタルアーカイブ活用ガイド
近年、家系図作成やルーツ調査において、インターネットの活用がますます重要になってきました。
特に欧米では、デジタルアーカイブと検索システムの整備が進んでおり、自宅にいながらルーツを辿る時代が到来しています。
日本でもこの流れは少しずつ加速しており、図書館・公文書館・大学などが史料の公開・検索機能の整備に力を入れています。
この記事では、家系図作成に役立つオンライン検索サイトやデジタル文献、データベースの活用方法を詳しくご紹介します。
【壬申戸籍と徴兵令の関係】戸籍制度は兵役制度のためにあった?
壬申戸籍(明治5年式戸籍)は、近代日本で初めて全国民を対象に作られた戸籍制度として知られています。
この戸籍制度が作られた背景には、徴兵制度の準備という重要な目的がありました。
この記事では、壬申戸籍と徴兵令の関係について、当時の社会背景とともにわかりやすく解説します。
【壬申戸籍の屋敷番号とは?】明治初期の戸籍整理と番号の付け方を解説
壬申戸籍(明治5年式戸籍)を読み解く際にしばしば目にするのが、「〇〇番屋敷」といった記載です。
これは、当時の住所を表すために使われていた「屋敷番号(家舗番号)」と呼ばれるものです。
この記事では、屋敷番号とは何か、どうやって決められたのか、なぜ使われなくなったのかについて、わかりやすく解説していきます。
【明治初期の身分法とは?】壬申戸籍とともに整備された制度
明治5年に編製が始まった「壬申戸籍」は、近代日本における最初の全国的な戸籍制度でした。
この戸籍の前後において、明治政府は近代国家としてふさわしい「身分制度」の整備を急ピッチで進めていきました。
この記事では、壬申戸籍と連動して布告・整備された身分法の主な内容を、時系列に沿ってわかりやすくまとめます。
【壬申戸籍とは?】明治時代に作られた最初の全国戸籍制度
「壬申戸籍(じんしんこせき)」は、明治5年(1872年)から全国で編製が始まった、日本で最初の近代戸籍です。
この記事では、壬申戸籍がどのように作られたのか、どんな特徴があったのかを分かりやすくまとめました。
大正4年式戸籍の特徴とは?
日本の戸籍制度は時代とともに何度も改正されてきました。
その中でも、大正4年(1915年)の改正によって作られた「大正4年式戸籍」は、
昭和23年(1948年)に新たな戸籍法が施行されるまで、長きにわたり使われてきた制度です。
この記事では、大正4年式戸籍の特徴や改正内容をわかりやすくご紹介します。
明治31年式戸籍とは?
前回に続き、今回は「明治31年式戸籍」についてです。
これは、1898年(明治31年)に施行された新しい民法にともない改正された
戸籍制度で、それまでの「明治19年式戸籍」が書き換えられ、
新たに「明治31年式戸籍」が編製されました。
“明治31年式戸籍とは?” の続きを読む