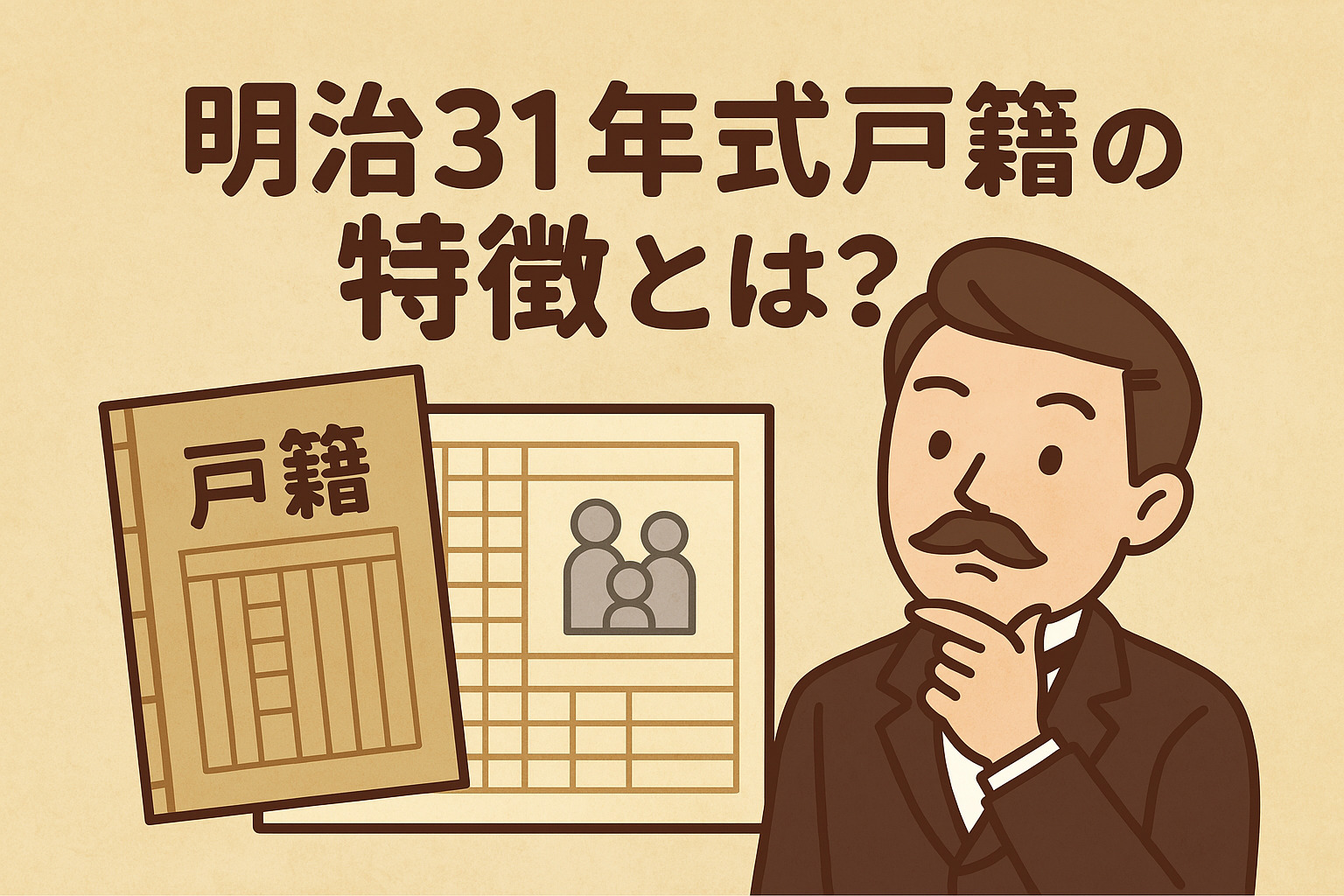前回に続き、今回は「明治31年式戸籍」についてです。
これは、1898年(明治31年)に施行された新しい民法にともない改正された
戸籍制度で、それまでの「明治19年式戸籍」が書き換えられ、
新たに「明治31年式戸籍」が編製されました。
この戸籍は大正3年(1914年)まで使われたもので、家制度の色濃い内容が反映されています。
今回は、明治31年式戸籍の特徴と背景について、わかりやすくまとめてみました。
🔍 明治31年式戸籍の主な特徴
① 戸籍の所管官庁が「司法省」に
それまで戸籍は内務省が管理していましたが、明治31年の改正で司法省の管轄へと移され、戸籍事務の監督は地方裁判所が担当するようになりました。
実務は引き続き、各地の戸籍役場にて「戸籍吏(こせきり)」が行っていました。
② 本籍地の取り扱いが柔軟に
この改正により、本籍地については「必ずしも現住所でなくても良い」と明文化されました。
本籍地は地番で表示される「地番主義」が徹底され、自由に設定できるようになったのです。
③ 「身分登記簿」の導入(ただし短命)
西洋法制にならい、戸籍とは別に「身分登記簿」が新たに設けられました。
ここには、出生・死亡・婚姻・養子縁組などの身分事項が記録されましたが、戸籍と内容がほぼ同じだったため実用性に乏しく、わずか16年後の大正4年に廃止されています。
④ 戸籍副本制度の強化
戸籍の正本は従来通り戸籍役場に保管され、副本(コピー)は地方裁判所(監督庁)に保管することになりました。
火災や紛失などによる再製のため、安全性が強化されたかたちです。
⑤ 戸籍の記載順序に「家制度」が色濃く反映
記載される家族の順番には、当時の冠婚葬祭における席順が反映されていました。
順序は次のようになります:
戸主
↓
戸主の直系尊属(祖父母 → 父母)
↓
戸主の配偶者
↓
戸主の直系卑属(子・孫など)とその配偶者
↓
戸主の傍系親族(兄弟姉妹など)とその配偶者
この記載順からも、「家の中心は戸主である」という考えが強く出ていることが分かります。
⑥ 戸主に強い権限が与えられていた
この時代、戸主には次のような強い権限が認められていました。
・居住地の指定権
・婚姻・養子縁組の同意権
もし家族が戸主の意に反して居所を移したり、結婚・縁組を行った場合、戸主はその者に対して扶養義務を免除され、離縁や復籍拒否を行えるという制度でした。
現代の感覚では想像しにくいですが、それほど「家」中心の社会制度だったのです。
📝 まとめ
・明治31年式戸籍は、民法の制定にあわせて大きく改正された戸籍制度
・戸籍の管理が司法省に移され、本籍地の取り扱いも柔軟に
・戸主を中心とした「家制度」が色濃く反映された構成が特徴
・副本制度や記載順など、現代に続く仕組みの基礎もここで整備されました
投稿者プロフィール
-
5代目製本業経営者。体を動かす事が趣味でジムに週5回通ってます。
詳しいプロフィールはこちら
最新の投稿
- 2025.10.16最近の5代目「氏(うじ)」と「姓(かばね)」の起源と変遷
- 2025.10.07最近の5代目鎖国と宗門改め――江戸時代の社会統制と国際関係
- 2025.09.26最近の5代目宗教と人口記録 ― 日本・イタリア・スウェーデンの比較から見えること
- 2025.09.25最近の5代目宗門改め帳 ― 日本独自の人口記録とその背景