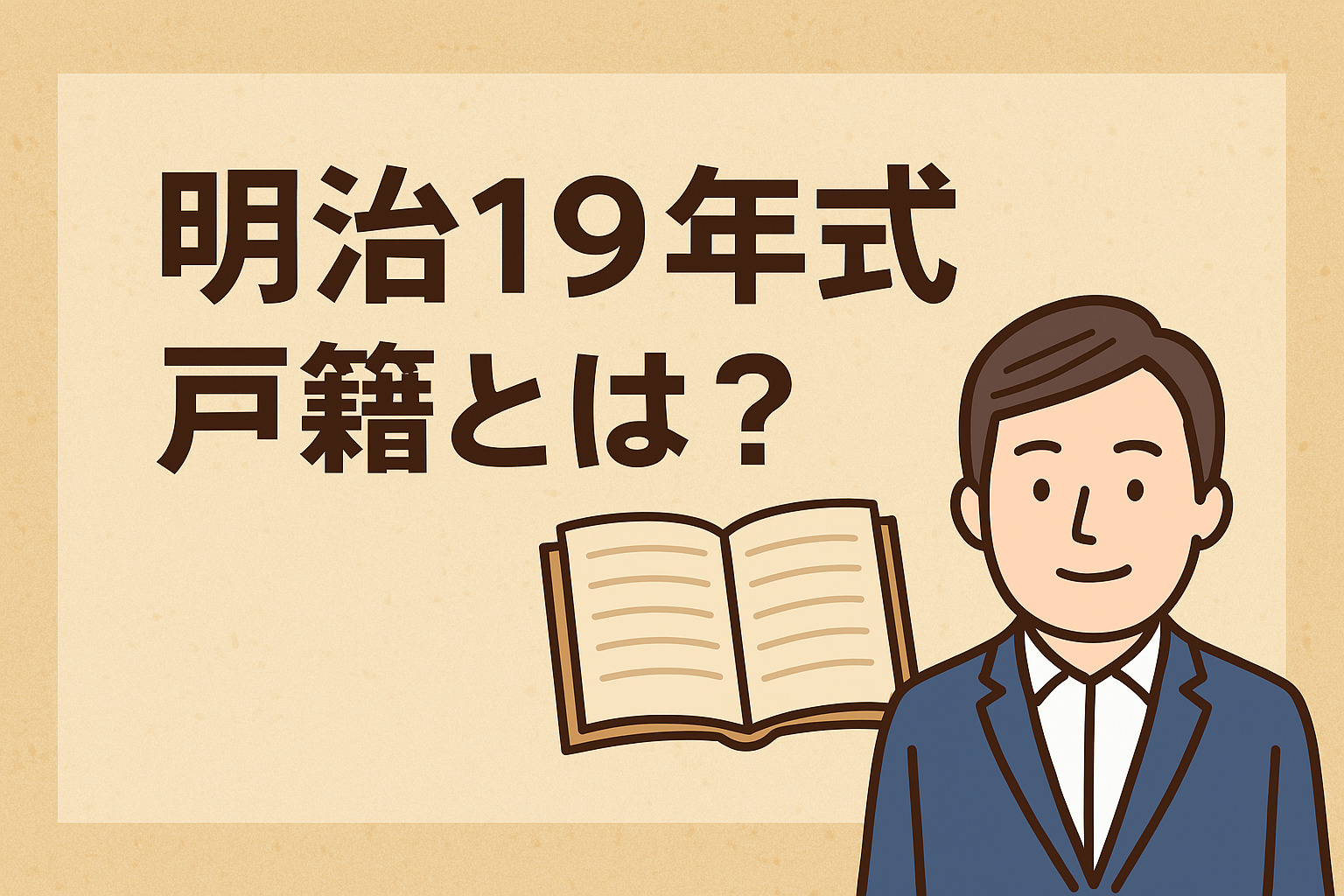家系図づくりや戸籍の調査をしていると、「明治19年式戸籍」という言葉に出会うことがあります。
この戸籍は、現在の戸籍制度に至るまでの大きな転換点の一つであり、家族のルーツを探る上でも非常に重要な資料となります。
今回は、明治19(1886)年に作られた戸籍の特徴や背景について、わかりやすくまとめました。
📜 明治19年式戸籍とは?
明治19年10月、内務省により明治4年の戸籍法の細則が制定され、それに基づいて新たに編成されたのが「明治19年式戸籍」です。
これを作る際にもととなった、明治5年に作られた戸籍は「明治5年式戸籍」と呼ばれ、改製されたため「改製原戸籍」という扱いになります。
🏠 地番表示へと変更された本籍の表記
それまで本籍の表記には「屋敷番号」が使われていましたが、地租(固定資産税)のための土地台帳整備に合わせ、
明治19年式戸籍では、**地所番号(地番)**での表示が指示されました。
ただし、地域によっては以前の屋敷番号がそのまま使われ続けたケースもありました。
📕 除籍簿制度の導入
明治19年式戸籍では、新たに「除籍簿制度」が設けられました。
戸籍内の全員が除籍になった場合
戸主が交代した場合
このようなケースでは、戸籍簿に朱線を引き、除籍簿へ移すことが義務づけられました。
📚 戸籍副本制度の導入
戸籍の安全な管理のため、戸籍簿の副本(コピー)を作成し、郡役所に保管する仕組みも導入されました。
災害などで本冊が焼失・紛失した場合には、この副本を使って戸籍を復元することができました。
🏘️ 寄留簿制度の整備
本籍地を移さずに転居した場合や、家族の一部が別の場所に住むようになった場合、
本籍地の役所では「出寄留簿」に、
居住地の役所では「入寄留簿」に記録するルールが定められました。
この寄留簿は、戸籍上の本籍と実際の居住地が異なる人の情報を補完するもので、
学齢簿(就学名簿)や印鑑証明の発行にも活用されていました。
⚠️ 届出の徹底と寄留法の制定
しかし、寄留届には当初罰則がなかったため、実際には届出をしない人が多数いました。
そのため、大正3(1914)年には「寄留法」が制定され、
「90日以上本籍外に居住する者は寄留者とみなす」という規定が設けられ、
届出を怠ると5円以下の過料が科されるようになりました。
また、明治後期以降の都市化により寄留者が増加したことを受け、
明治31年の戸籍法では「本籍は必ずしも住所地でなくてもよい」と変更されました。
📝 届出義務の強化
以下のような身分に関する重要な事柄については、戸籍への届出が義務化されました。
・出生
・死亡
・失踪者の復帰
・廃戸主・廃嫡
・改名・復姓
・身分の変動 など
これらの届出は10日以内とされ、違反した場合は1円25銭以下に処されました。
昔の時代から色々と規則があったのだと感じました。。。
投稿者プロフィール
-
5代目製本業経営者。体を動かす事が趣味でジムに週5回通ってます。
詳しいプロフィールはこちら
最新の投稿
- 2025.10.16最近の5代目「氏(うじ)」と「姓(かばね)」の起源と変遷
- 2025.10.07最近の5代目鎖国と宗門改め――江戸時代の社会統制と国際関係
- 2025.09.26最近の5代目宗教と人口記録 ― 日本・イタリア・スウェーデンの比較から見えること
- 2025.09.25最近の5代目宗門改め帳 ― 日本独自の人口記録とその背景