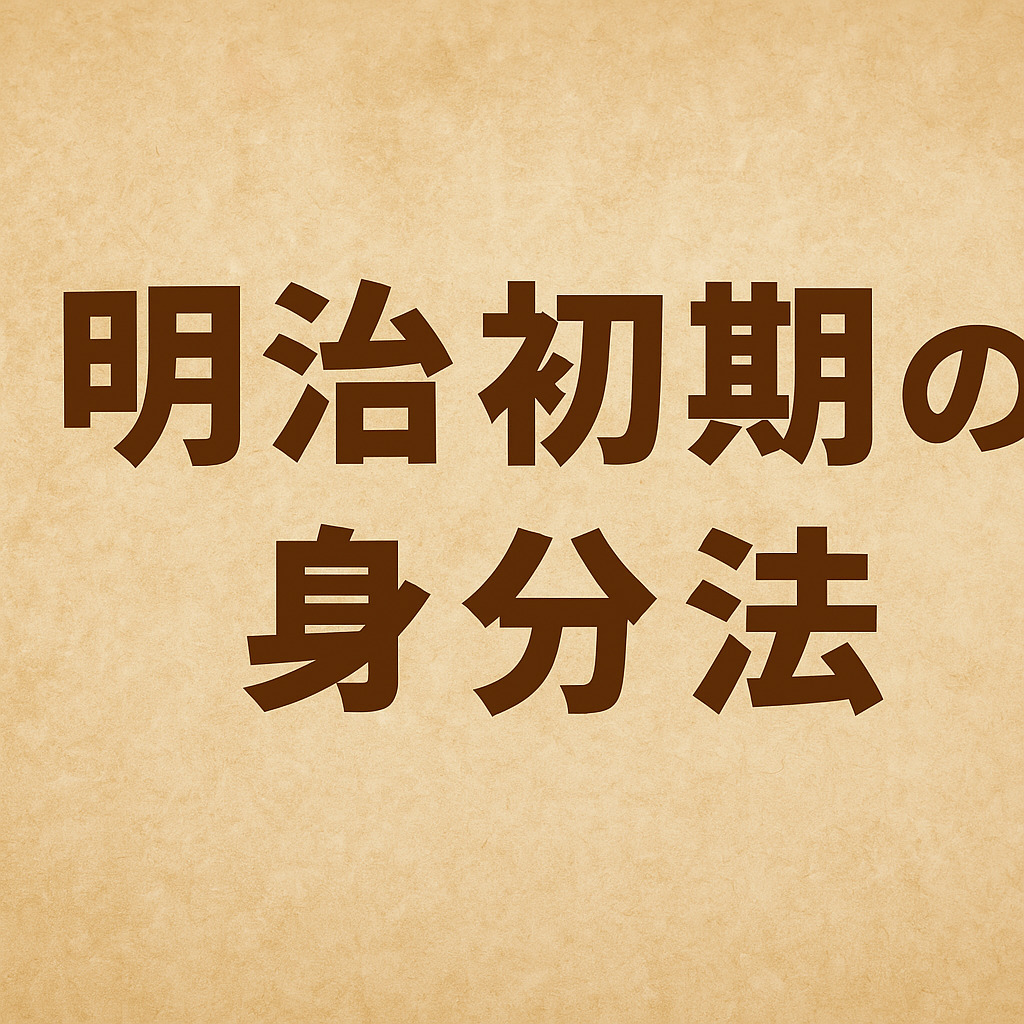明治5年に編製が始まった「壬申戸籍」は、近代日本における最初の全国的な戸籍制度でした。
この戸籍の前後において、明治政府は近代国家としてふさわしい「身分制度」の整備を急ピッチで進めていきました。
この記事では、壬申戸籍と連動して布告・整備された身分法の主な内容を、時系列に沿ってわかりやすくまとめます。
📜 明治政府が整備した身分法の主な内容
● 族称(華族・士族・平民)を超えた婚姻の自由
身分に関わらず、華族・士族・平民間の婚姻が自由に認められた
外国人との婚姻も同様に自由化された
● 合家(ごうけ)制度の導入と廃止
戸主が死亡し、相続人が幼少や女性で家の維持が困難な場合、本家や親族関係にある家と1つの戸籍に合併することが認められた
この制度は主に士族層が利用し、両家に年金が支給されていたが明治9年(1876年)に廃止
● 婚姻制度の明文化
婚姻は戸籍に登録して初めて法的に有効
妻が離婚を望んでも夫が応じない場合、父親や兄弟などが代理人として裁判所に訴えることが可能とされた
● 私生子の扱い
妻や妾でない女性が出産した子は「私生子」とされ、その女性が引き取るものとし、父への強制認知は不可
● 僧侶の生活の自由化
僧侶・尼僧の肉食、妻帯、蓄髪(髪を伸ばすこと)は自由とされた
● 家制度の確立と相続ルール
家督相続は原則として長男による「総領相続」(単独相続)とする
**女戸主(女性の戸主)**も認められた
● 苗字・家の制度の整備
苗字が不明な者には、新たに苗字を名乗ることが許可された
分家・廃家も認められた
※廃家:分家をやめて本家に復帰すること
● 絶家(ぜっけ)の規定
単身戸主が死亡または除籍された後、6か月以内に相続届がなければ「絶家」となる
● 縁女(えんじょ)の制度
縁女とは、将来ある家の男子と結婚する約束がある幼女(いいなづけ)のこと
養子と縁女の結婚予定が破談になった場合、養子が離縁すると縁女も実家へ復籍した
この制度は明治31年に廃止され、その後一部が養女に切り替えられた
📝 まとめ
壬申戸籍が編製された明治初期、明治政府は国民の身分・婚姻・家族制度に関する一連の法整備を急速に進めました。
これらの法律は、すべて明治31年(1898年)に制定された「旧民法」施行まで有効とされ、現在の家族法や戸籍制度の基盤となる重要な役割を果たしました。
投稿者プロフィール
-
5代目製本業経営者。体を動かす事が趣味でジムに週5回通ってます。
詳しいプロフィールはこちら
最新の投稿
- 2025.10.16最近の5代目「氏(うじ)」と「姓(かばね)」の起源と変遷
- 2025.10.07最近の5代目鎖国と宗門改め――江戸時代の社会統制と国際関係
- 2025.09.26最近の5代目宗教と人口記録 ― 日本・イタリア・スウェーデンの比較から見えること
- 2025.09.25最近の5代目宗門改め帳 ― 日本独自の人口記録とその背景