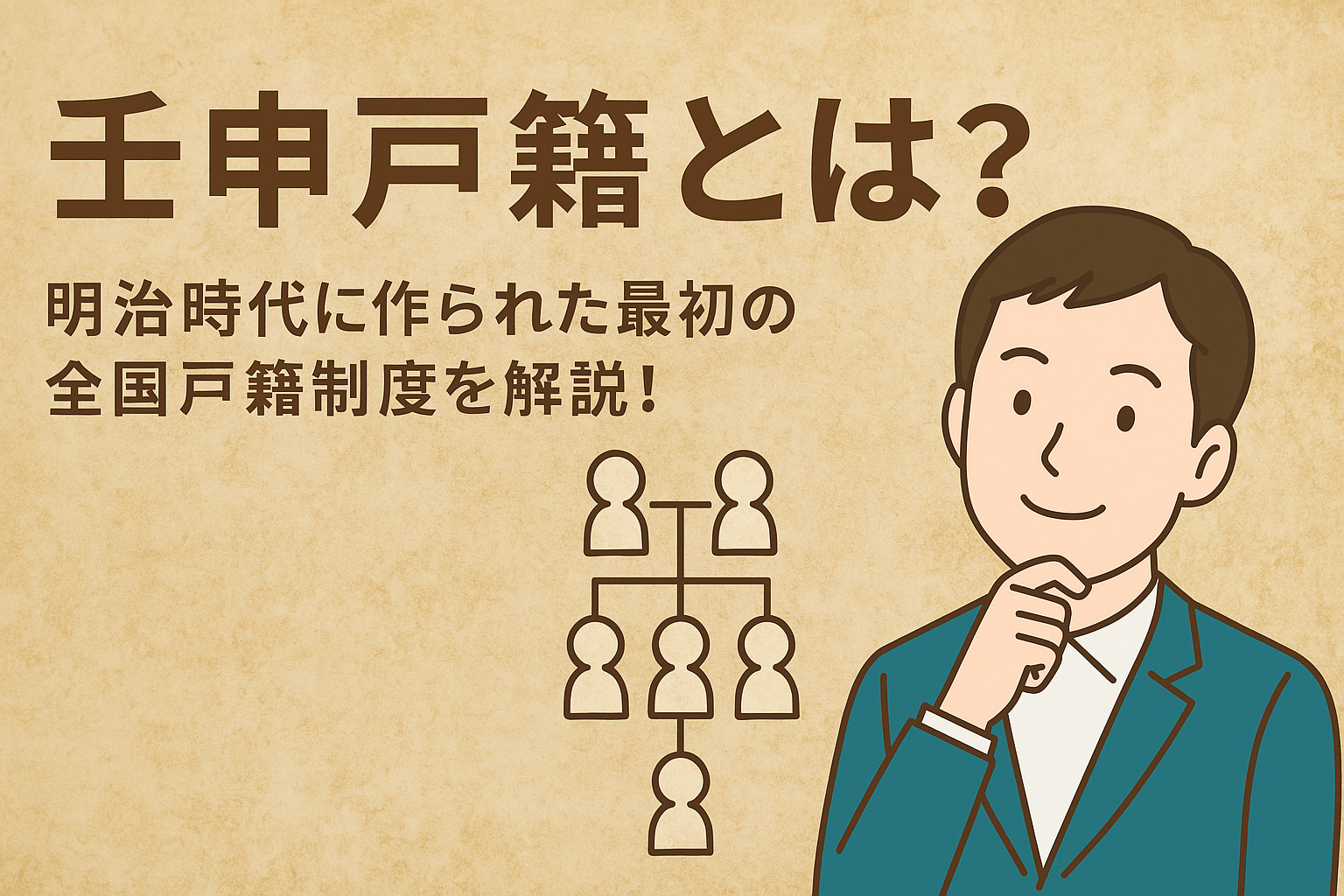「壬申戸籍(じんしんこせき)」は、明治5年(1872年)から全国で編製が始まった、日本で最初の近代戸籍です。
この記事では、壬申戸籍がどのように作られたのか、どんな特徴があったのかを分かりやすくまとめました。
📘 壬申戸籍とは?
明治4年(1871年)に戸籍法が布告され、それに基づき翌年の明治5年から戸籍の作製が始まりました。
この年の干支(十干十二支)が「壬申(みずのえ・さる)」であったことからこの戸籍は「壬申戸籍」と呼ばれています。
壬申戸籍の作製は、1872年2月1日から開始され、1886年10月15日までに全国で編製が完了しました。
📌 壬申戸籍の主な特徴
① 全国民を登録対象に
皇族・天皇を除くすべての国民を戸籍に登録
戸籍は住所地単位で作成されました
② 戸籍事務は国直轄の業務
戸籍は国が直接管理
地方では複数の町村をひとつの「戸籍編成区」とし、戸長(こちょう)・副戸長が配置されました
戸長はもともと庄屋や名主などから選ばれ、戸籍専任の吏員とともに戸籍業務にあたっていました
③ 編製後は6年ごとに調査(実際には未実施)
原則として6年ごとに戸口調査(今でいう国勢調査)を行い、それをもとに戸籍を更新する予定でしたが、転居などが多く、実際には実施されなかったとされています
④ 屋敷番号で戸籍を管理
戸籍簿は町村単位で作成され、その町村内の屋敷(家)を「〇〇番屋敷」「〇〇番戸」など、屋敷番号順に綴じられていました
⑤ 附籍制度:血縁以外の人も同居者として記録
同じ家に住んでいるすべての人を1つの戸籍に記載
血縁関係がなくても、苗字が異なる者・使用人・養育されていた者なども含まれており、これらの人々は「附籍者(ふせきしゃ)」と呼ばれました
例:士族の家に同居していた下働きの者、親戚の子など
附籍制度は、明治31年の旧民法で廃止され、苗字が異なる者は別の戸籍に編製されるように変更されました
⑥ 記載順に家族構成のヒエラルキーが反映
戸籍には、以下の順番で家族構成が記録されていました:
戸主
戸主の直系尊属(父母・祖父母など)
戸主の配偶者
戸主の直系卑属(子・孫など)
直系姻族(妻の両親など)
兄弟姉妹
傍系親族(兄弟の子など)
⑦ 妾(めかけ)の記載もあった
明治初期には、妾(側室)やその子どもも戸籍に記載されました
妾が産んだ子は、「妾腹」や「妾の子」といった記載がされることもありました
明治8年には妾も妻と同じく“公生子”を産むことができるとされ、
父の認知なしで戸籍に登録可能とされましたが、
明治15年に制度は廃止され、その後は非嫡出子として扱われるようになります
⑧ 戸籍に記載された情報は非常に詳細
年齢
戸主との続柄
婚姻・離婚・養子縁組・離縁
族称(華族・士族・平民など)
職業、宗旨(宗派)、菩提寺、氏神
犯罪歴、戸主の印鑑
地域によっては田畑の面積や家畜の数、死因まで記載されていることも!
📝 まとめ
壬申戸籍は、明治政府が近代国家として全国民を管理するために作成した最初の戸籍です。
現代の戸籍とは形式も制度も大きく異なりますが、当時の家族構成や社会状況を知る貴重な手がかりとなります。
血縁以外の人も記載されていた「附籍」制度
妾の記載や宗教・職業・犯罪歴など多様な情報
現在では原則、閲覧・交付はできません(個人情報保護のため)
投稿者プロフィール
-
5代目製本業経営者。体を動かす事が趣味でジムに週5回通ってます。
詳しいプロフィールはこちら
最新の投稿
- 2025.10.16最近の5代目「氏(うじ)」と「姓(かばね)」の起源と変遷
- 2025.10.07最近の5代目鎖国と宗門改め――江戸時代の社会統制と国際関係
- 2025.09.26最近の5代目宗教と人口記録 ― 日本・イタリア・スウェーデンの比較から見えること
- 2025.09.25最近の5代目宗門改め帳 ― 日本独自の人口記録とその背景