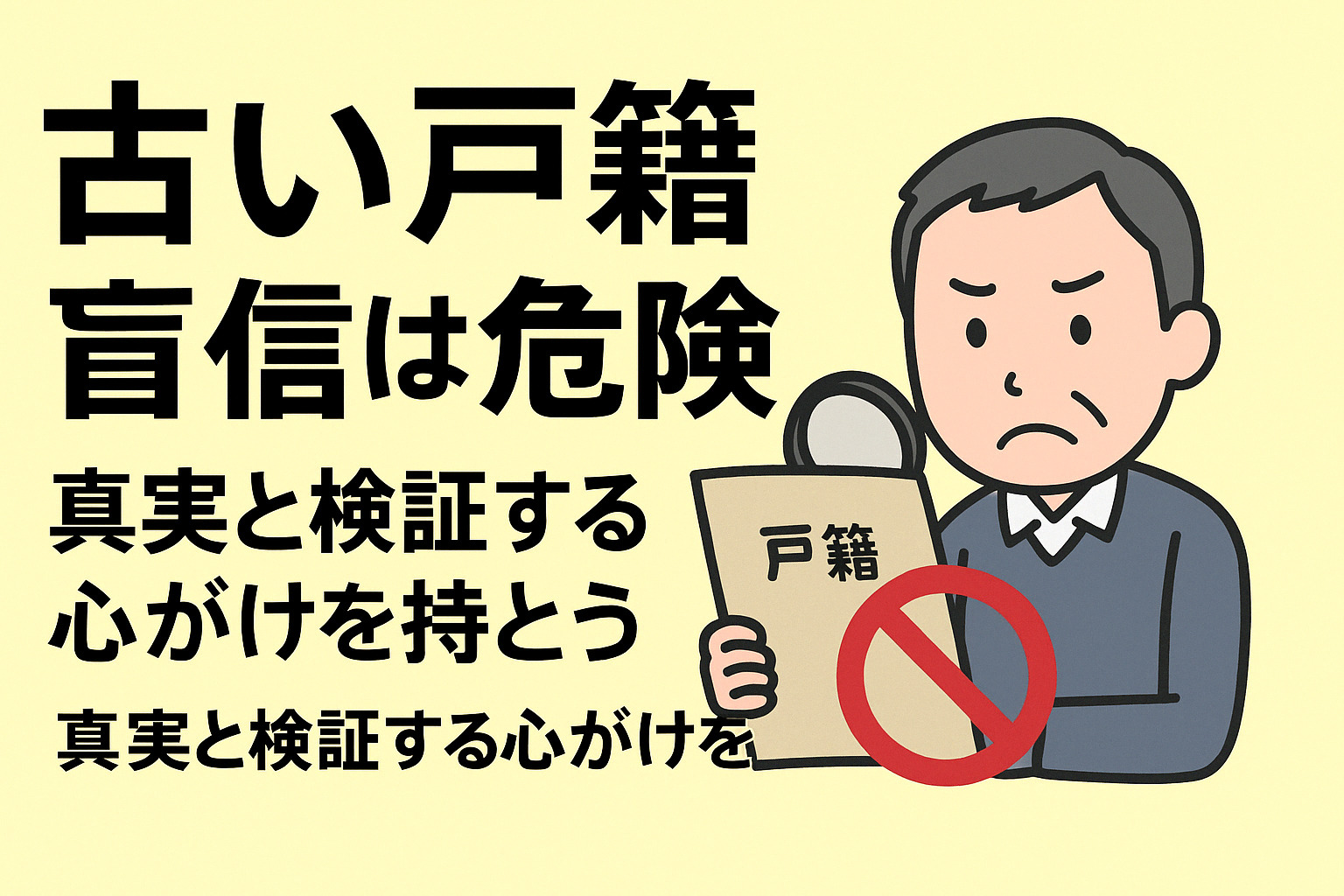家系図作成において「戸籍=正確な公的記録」として捉えられがちですが、実は古い戸籍の記載には数多くの誤りや意図的な改変が含まれていることがあります。
特に戦前・明治時代の戸籍には、信頼性に限界があることを理解し、正しく扱う意識がとても重要です。
📜 戸籍は“オリジナル”の一次資料ではない
明治5年(1872年)に作成された「壬申(じんしん)戸籍」をはじめ、明治・大正期の戸籍は、当時の住民が自己申告で届け出た情報をもとに、戸籍吏が手書きで作成していました。
そのため、記録に誤記・遅れ・恣意的な書き換えが生じることも珍しくありません。
🕵️♂️ 戸籍に見られる“典型的な問題点”
① 養子と実子の“すり替え”
壬申戸籍では養子だった人物が、明治19年式戸籍では実子として記載されている例が確認されています。
② 生没年や続柄の食い違い
出生・死亡年が違っていたり、続柄が変わっていたりすることも。
③ 届出の大幅な遅れ
冬場に出生したため、雪解け後の春に出生届を出した、出生から数年経ってようやく届け出たケースもあります。
これにより、実際の誕生日と戸籍上の誕生日が異なる例が数多く見られます。
④ 死亡届も遅延または未提出
自宅で亡くなるケースが多かった当時、届出が遅れたり、出されなかったりしたままの例も多数存在します。
💡 「戸籍の矛盾」は、こうして生まれる
・届出者と戸籍吏が同じ村内の住人だったため、地縁・血縁関係から忖度や改変が行われやすかった
・戸籍の転記・改製時に、誤字脱字や解釈違いが発生
・戦争・災害で戸籍原本が消失した際には、聞き取りだけで再作成されたケースも
・住民が意図的に情報を書き換える(例:婿養子名義を使って出生の整合性を取る)ことすらありました
📌 法務省も認める誤記の存在
法務省の調査でも、現在の除籍のおよそ30%には誤記・脱字があるとされています。
これは転記作業の際の誤りや、古い筆記による誤読が主な原因です。
❗ 盲信は危険。検証こそが大切!
家系図を戸籍だけを根拠に作ってしまうと、誤った人物関係をそのまま“家系の真実”として後世に残してしまうリスクがあります。
そのため、戸籍はあくまで“材料”であり、検証が不可欠です。
✅ アメリカの系図学会「BCG」が提唱する“系図検証の5原則”
米・系図学者認定委員会(Board for Certification of Genealogists)が提唱する「系図証明基準」では、以下の5つの手順が重要とされています。
①適度に網羅的な情報の収集
②引用元の明記(追試の保証)
③情報の徹底的な分析と関連付け
④矛盾する証拠の解決
⑤合理的で筋の通った結論
🧩 家系図作成は“ここから”が本番
古い戸籍を取得して系図を書き上げた時、「これで完成」と思ってしまう方も多いですが、本当のスタートはここからです。
戸籍とは料理で言えば“食材”。
ただ並べただけでは料理にはなりません。
資料を組み合わせ、背景を調べ、矛盾を検証しながら“真実の系図”を紡ぐ姿勢が大切です。
✨ まとめ
・戸籍の内容は必ずしも事実とは限らず、特に戦前・明治期は慎重に扱うべき
・一次史料ではなく、誤記・遅延・改変などが生じている可能性がある
・戸籍を“材料”とし、複数資料で検証・照合する姿勢が大切
・戸籍は完成形ではなく、“家系図作りの出発点”と考えましょう
もし、戸籍、ルーツ探しでお困りがあれば、いつでもお問い合わせください◎
投稿者プロフィール
-
5代目製本業経営者。体を動かす事が趣味でジムに週5回通ってます。
詳しいプロフィールはこちら
最新の投稿
- 2025.10.16最近の5代目「氏(うじ)」と「姓(かばね)」の起源と変遷
- 2025.10.07最近の5代目鎖国と宗門改め――江戸時代の社会統制と国際関係
- 2025.09.26最近の5代目宗教と人口記録 ― 日本・イタリア・スウェーデンの比較から見えること
- 2025.09.25最近の5代目宗門改め帳 ― 日本独自の人口記録とその背景