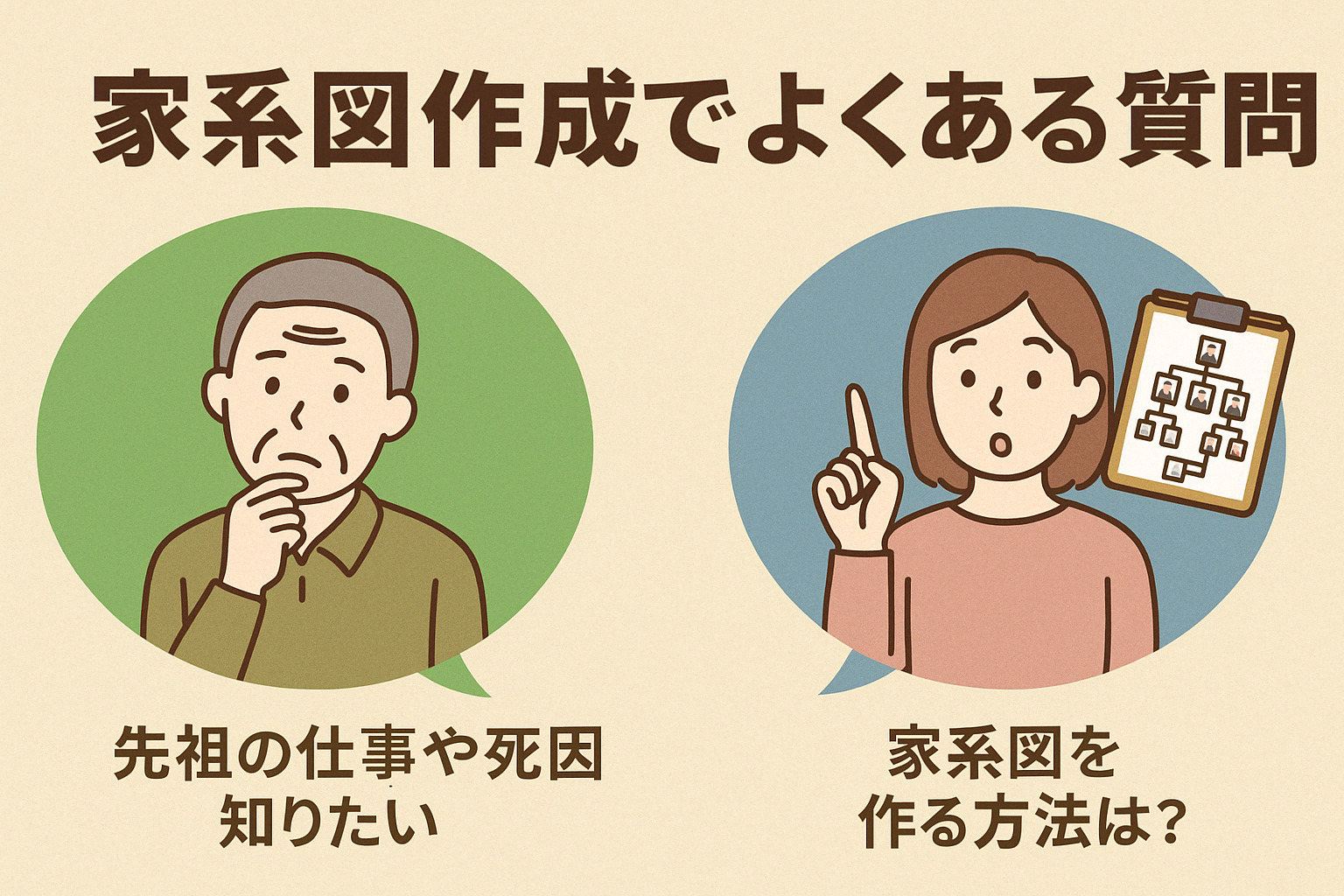家系図を作成する過程で、「ご先祖がどんな仕事をしていたのか」「亡くなった理由を知ることはできるのか」といった、
より深い情報に興味を持たれる方も多いようです。
今回は、先祖の職業や死因を調べるための手がかりや資料についてご紹介します。
❓Q:先祖の仕事を知ることはできますか?
✅ A:戸籍には記載がありませんが、他の資料から推測できることがあります。
除籍謄本には、職業に関する記載は基本的にありません。
ただし、以下のような情報からある程度の推測が可能です。
① 本籍地の場所から推測する
戦前の本籍地は、基本的に実際に住んでいた住所でした。そのため、
農村部 → 農家である可能性が高い
都市部 → 商人・職人・武士などの町人・士族系の職業の可能性
が考えられます。
② 学校の記録に職業が残っていることも
明治5年(1872年)に「学制」が公布され、全国に小学校が設置されました。
この頃の**就学記録(学籍簿)**の中には、生徒の保護者(父親)の職業が記載されている場合があります。
地域の教育委員会や図書館、公文書館に問い合わせることで、こうした資料に出会えることがあります。
❓Q:先祖の死因を知ることはできますか?
✅ A:戸籍には死因は書かれていませんが、他の手がかりを使って調べることができます。
除籍謄本には、「亡くなった日付」や「死亡地」は記載されていますが、死因そのものは明記されていません。
そこで、次のような方法で死因を調べることが可能です。
① 当時の新聞や市町村史を確認する
亡くなった年・地域を手がかりに新聞や地域史を調べると、
・コレラなどの感染症が流行していた時期だった
・戦争や災害があった年だった
など、状況的な死因を推測できる場合があります。
② お寺の過去帳に記録されていることも
ご先祖が檀家であったお寺には、戒名・死亡年月日・享年・死因などが記された「過去帳」が残されている場合があります。
ただし、すべてのお寺に死因の記載があるとは限りません。
③ 家族・親族の言い伝えがもっとも有力
昔の記録には残されていないことでも、一族に代々語り継がれてきた話が、最も有力な情報源となることがあります。
「祖父は肺病で亡くなったと聞いている」「戦地で行方不明になったと聞いた」など、親戚や家族の年長者に聞いてみることをおすすめします。
④ 除籍の記載から推測できる場合もある
例として、
・「野戦病院で死亡」→ 戦病死
・「〇〇沖にて死亡」→ 船の沈没や戦災による死亡
など、死亡地の表記からある程度の事情が読み取れるケースもあります。
投稿者プロフィール
-
5代目製本業経営者。体を動かす事が趣味でジムに週5回通ってます。
詳しいプロフィールはこちら
最新の投稿
- 2025.10.16最近の5代目「氏(うじ)」と「姓(かばね)」の起源と変遷
- 2025.10.07最近の5代目鎖国と宗門改め――江戸時代の社会統制と国際関係
- 2025.09.26最近の5代目宗教と人口記録 ― 日本・イタリア・スウェーデンの比較から見えること
- 2025.09.25最近の5代目宗門改め帳 ― 日本独自の人口記録とその背景