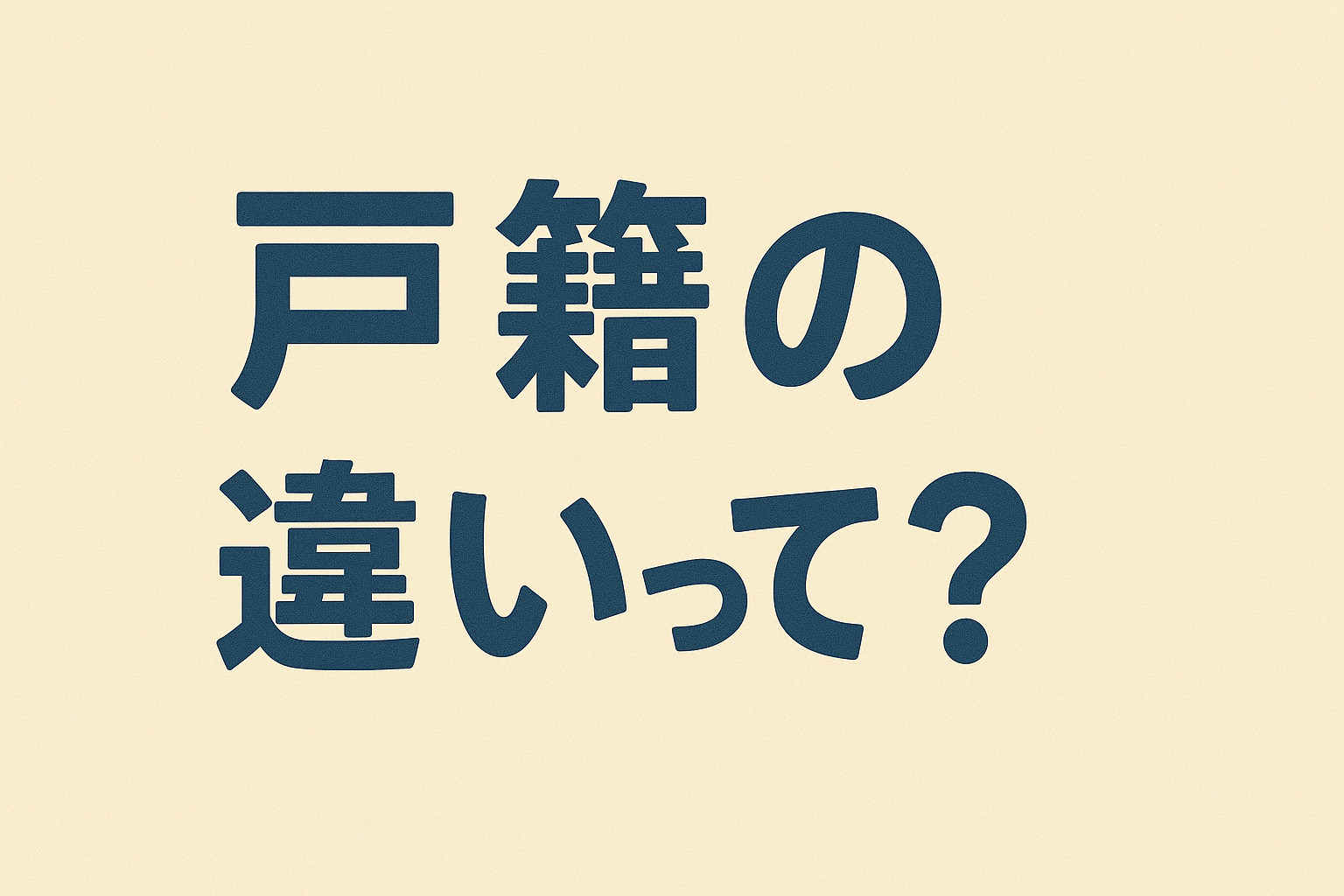家系図づくりを始めようと思ったとき、まずぶつかるのが「戸籍」についての壁です。
今回は、基本的な3つの戸籍の種類をわかりやすくまとめてみました!
①戸籍謄本(こせきとうほん)
これは、現在も有効な最新の戸籍です。
基本的に横書きで読みやすく、今生きている人が載っているのが特徴です。
現在は戸籍のコンピューター化が進んでおり、
戸籍謄本 =「全部事項証明書」
戸籍抄本(個人分)=「個人事項証明書」
という名称でも使われています。
戸籍謄本は、結婚や相続、パスポート申請などでも必要になる書類。
そして実は、日本人であることの証明でもあるんです。
②改製原戸籍(かいせいげんこせき/原戸籍)
「かいせいげんこせき」と読み、略して「原戸籍(はらこせき)」と呼ばれることもあります。
これは、戸籍の形式(書き方や内容のルール)が変わったときに、古い形式のまま閉じられた戸籍のこと。
つまり、「戸籍が新しく切り替えられる前の記録」です。
家系図を作るときには、この古い戸籍に過去の家族の記録が残っていることが多く、非常に重要な資料となります。
③ 除籍謄本(じょせきとうほん)
「除籍(じょせき)」とも呼ばれます。
これは、その戸籍に載っていた全員が、結婚で別の戸籍に移った、転籍した、亡くなった
といった理由で誰もいなくなった場合に発行される戸籍です。
簡単にいうと、「空っぽになった戸籍」ですね。
戸籍について学んでいく中で、特に重要だと感じたルールがあります。
それは、戸籍の情報は “引き継がれない” という点です。
たとえば、こんなケースがあります。
例)4人家族の兄が結婚して別戸籍になった場合
もとの戸籍:
父、母、兄、弟
その後の状態:
戸籍①:父、母、弟(兄は除籍)
戸籍②:兄、兄の妻(新戸籍)
このように、ある人が戸籍から抜けると、新しい戸籍にはそれ以前の家族の記録は載っていません。
つまり、1通の戸籍だけでは先祖をたどることができないのです。
過去にさかのぼって、いくつもの戸籍を集めていく必要がある。
それが、家系図づくりがちょっと大変だと感じる理由でもあるのだと、実感しました。
戸籍の仕組みを知ることで、家系図づくりがグッと進めやすくなります。
少しでも参考になれば嬉しいです!
何かあればいつでもご相談ください◎
投稿者プロフィール
-
5代目製本業経営者。体を動かす事が趣味でジムに週5回通ってます。
詳しいプロフィールはこちら
最新の投稿
- 2025.10.16最近の5代目「氏(うじ)」と「姓(かばね)」の起源と変遷
- 2025.10.07最近の5代目鎖国と宗門改め――江戸時代の社会統制と国際関係
- 2025.09.26最近の5代目宗教と人口記録 ― 日本・イタリア・スウェーデンの比較から見えること
- 2025.09.25最近の5代目宗門改め帳 ― 日本独自の人口記録とその背景